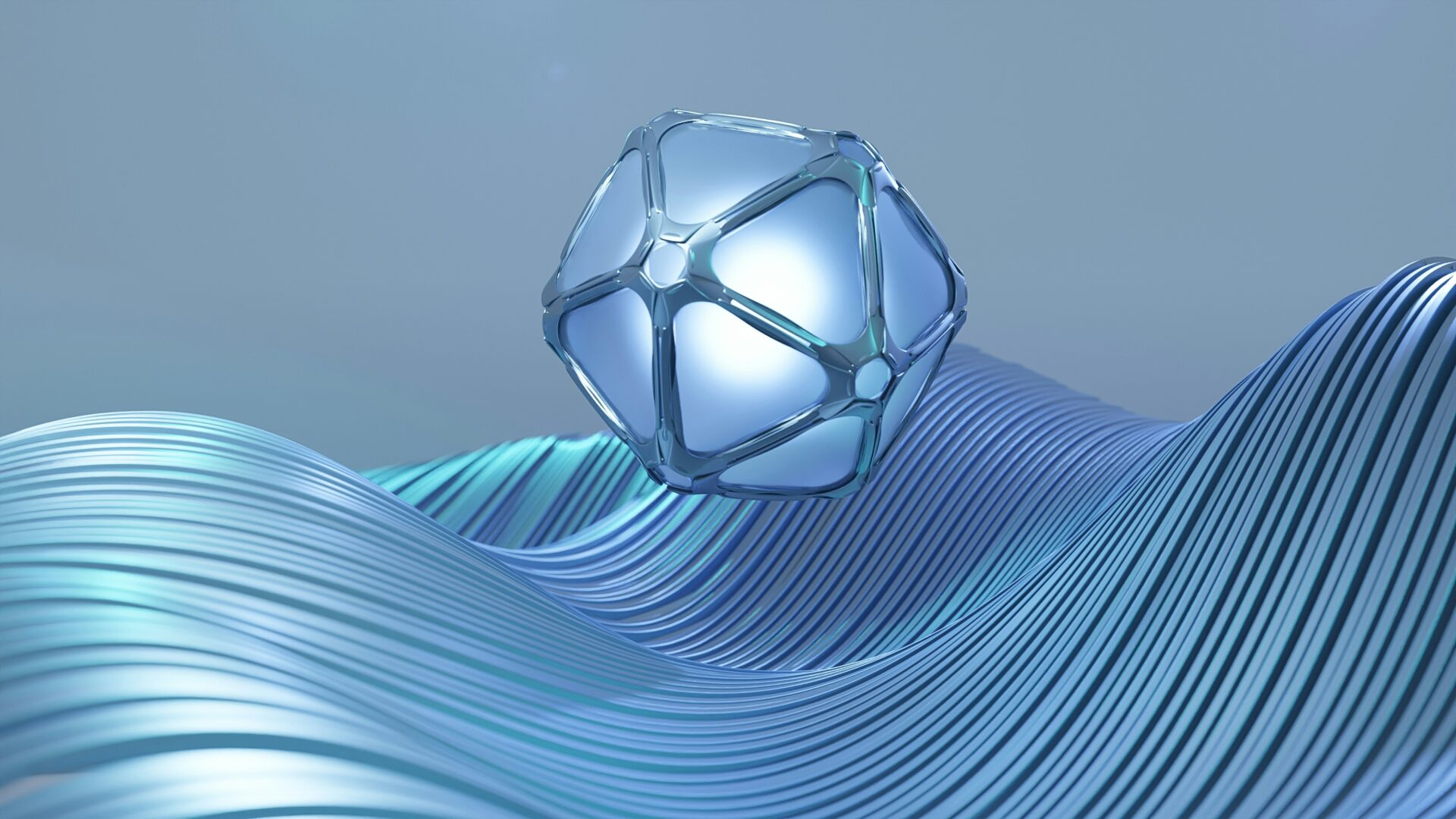■まずは結論から
- いま(2025年)個人は原則「雑所得・総合課税」のまま。最大55%の累進課税、損失繰越なし(他の雑所得等の通算制限あり)。改革は検討・要望段階が中心です。
- 法人は2024年度改正で前進。自社発行や一部の譲渡制限付きトークンの期末時価評価課税の見直しが進み、評価方法の選定ルールが整備されました。
- 制度面では追加の大改正も検討。FSAは暗号資産を金融商品として位置付け、インサイダー規制等を適用する法改正の準備を進めています(国会提出は最短で2026年想定)。
※今回の記事は、中級者~上級者向けの内容となっています。読んでもよくわからない方は、引き続き「ビットコイン・イーサリアムのガチホ」でOK。下手に動かさないで大丈夫です。
目次
いま有効な変更点(主に法人向け)
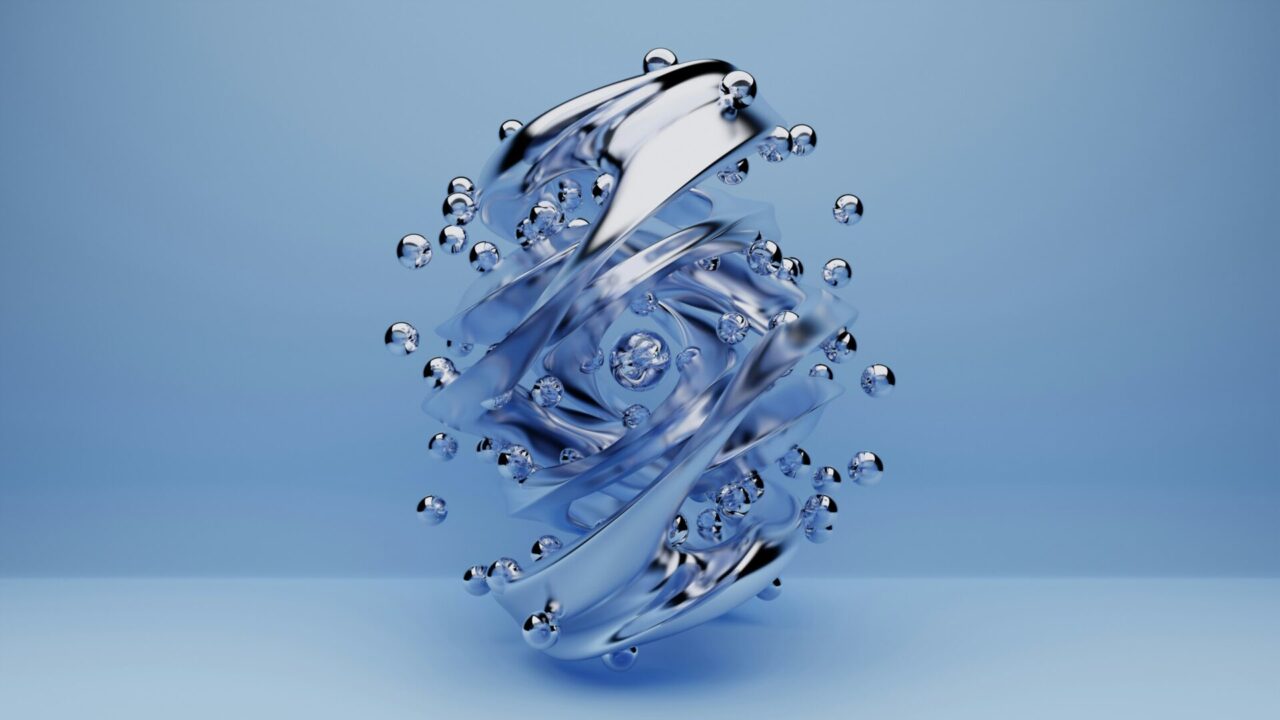
期末時価評価の見直しが進展(2024年度)
■自社発行トークンや、一定の譲渡制限が付く暗号資産について、期末時価評価課税の対象外とできる範囲が拡大。
■評価方法(時価法/原価法)の選定・変更届出ルールが明確化。
これは、発行体・Web3事業会社にとって、含み益課税の負担軽減につながる改正です。
これから見込まれる改正テーマ(個人向けの“検討中”論点)
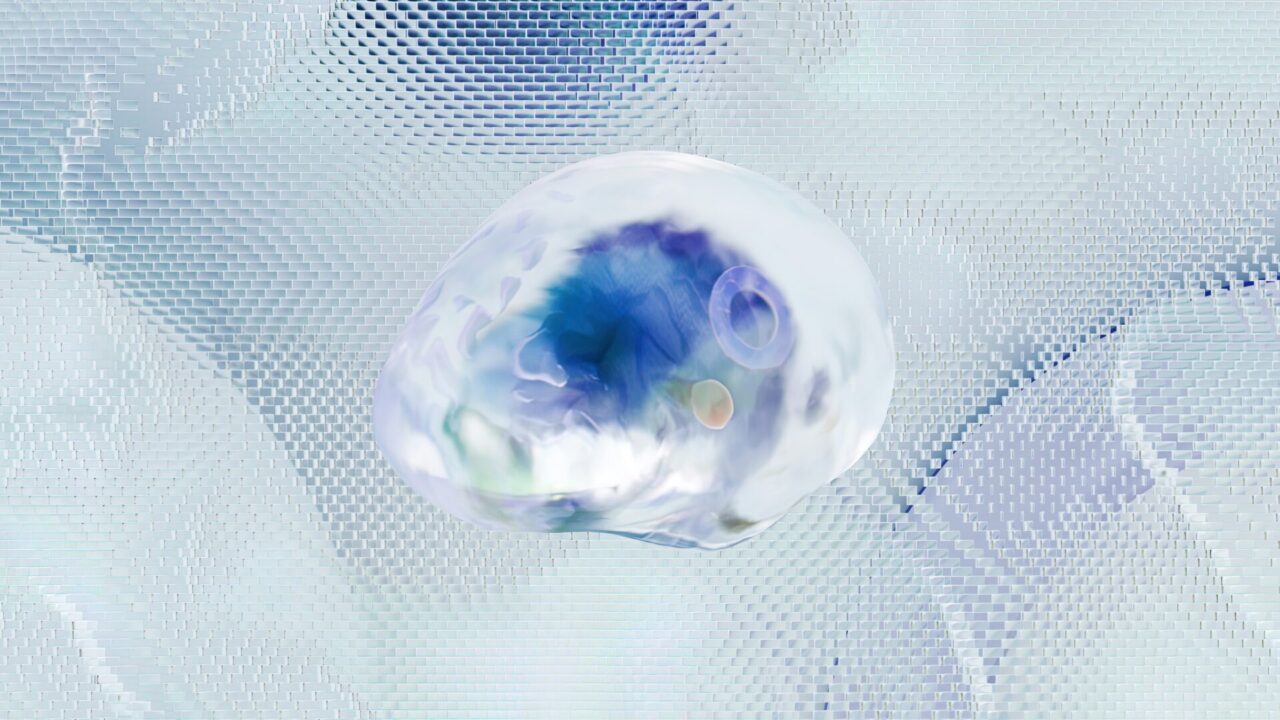
各業界団体や事業者の要望、解説記事、当局の審議資料から、主に次の3つが焦点です。
1) 20%の申告分離課税+損失繰越(3年)
現行の「雑所得・総合課税(最大55%)」から、株式の譲渡益と同様の20.315%一律・分離課税へ移行する案が継続検討中。
損失の翌年以降繰越(3年)もセットで議論されています。現時点では導入時期は未確定。
2) 暗号資産↔暗号資産の交換時課税の繰延べ
DeFiやNFTで避けづらい「都度課税」問題の緩和(交換時点では課税を繰延べ、最終的な換金時に課税)も議題に。
産業振興の観点から要望が出ています(法制化はこれから)。
3) 制度・監督の強化(FIEA改正)
暗号資産に金融商品としての地位を与え、インサイダー規制や情報開示を強化する方向。
ETFや有価証券型トークンとの整合も意識した枠組みで、投資家保護と市場の信頼性向上が狙い。
提出は早くて2026年見込み。
補足:2025年は金融審議会でも利用者動向や制度課題の洗い出しが進み、専門WG設置などの動きが見られます。
投資家が受ける実務インパクト(想定)
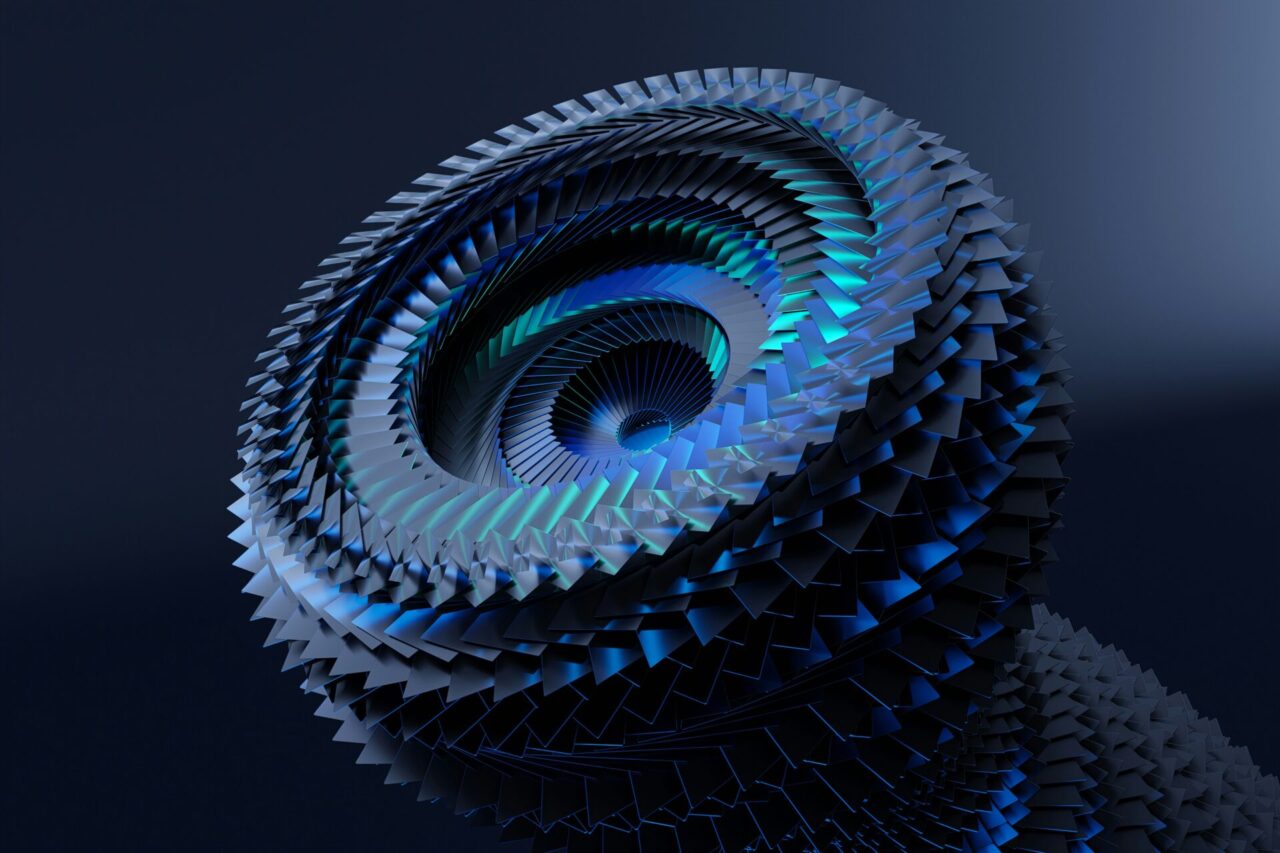
- 分離課税が実現した場合
- 税率は一律20.315%へ(所得合算なし)/損失繰越3年が可能に。税コストの見通しが立てやすくなり、新規参入の追い風。
- 交換時課税の繰延べが実現した場合
- DeFi・NFTの取引設計がシンプルに。過度な実現益の発生を避けやすく、国内ユーザーの活動が活発化する可能性も。
- FIEA改正(インサイダー規制等)が進む場合
- 取引所・発行体・関係者の情報管理や開示義務が強化。その分、市場の透明性・信頼性が上がる期待。
いずれも法案成立・施行が確定してから反映されます。報道や要望段階と実際の施行はタイムラグがある点に注意。
2025年にやっておくと良い“3つの備え”

- 取引履歴の一元管理
- 取引所・ウォレット・DeFiの履歴を月次でエクスポートして保管。国税庁の計算書フォーマット(移動平均法・総平均法)も参照。
- 税制の変化を前提に“売却・利確計画”をシミュレーション
- 分離課税が実現した場合の税額/損失繰越の活用可否を、現行制度と二本立てで試算。
- 法人・個人の“切り分け”を再点検
- 事業としてのトークン活用や発行をするなら、期末評価の適用関係や届出を確認(会計士・税理士と相談)。
まとめ:今は“過渡期”。最新情報を追いつつ、動ける準備を

- 個人課税の大枠は未だ現行維持だが、分離課税・損失繰越・繰延べなどの前向きな議論が加速
- 法人課税は改善が進み、発行体の環境は良化
- 市場制度は“投資家保護と透明性”の方向へ(金融商品化・インサイダー規制など)
いまは“法制確定前夜”。
「決まってから動く」のではなく、決まっても困らない準備をしておくのが正解です。